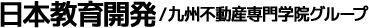修学旅行の正体(上) 後絶たぬ中国詣で
ライセンスメイト篇
平成15年1月号「人と意見 シリーズ修学旅行 教程その1」
歓迎の真意
小学校、中学校、高等学校では、卒業前に修学旅行が行われる。辞書には「児童、生徒らに日常経験しない土地の自然・文化などを見聞、学習させるために教職員が引率して行う旅行」とあり、日本独特の学校行事なのだそうだ。
修学旅行の特徴的な傾向の一つに、海外修学旅行の増加が挙げられる。十年前の平成四年度は全国で五万人を超える程度だった参加者が、昨年度はその四倍の二十万人を超えている(財団法人日本修学旅行調べ)。
確かに海外修学旅行は、子供たちの目を世界に開かせる絶好の機会である。しかし、現在の海外修学旅行の在り方には大きな間題が潜んでいる。どういうことかというと、目的地の選定如何によっては、非常に歪んだ形の修学旅行になってしまうからだ。
海外修学旅行で中国に行くケースが後を絶たない。昨年度の海外修学旅行実施状況を見ても、目的地別でトップの韓国、二位のオセアニアに次いで多かったのが中国だ。これは、実に憂慮すべき現象といわざるをえない。因みに四位以下は韓国・中国以外のアジア、北アメリカ、ヨーロッパ、その他、だったという。
中国への修学旅行は、海外修学旅行の目的である国際化教育と、一種の流行語にさえなっている「日中友好」の抱き合わせで実施される。人的交流を広げる、将来の経済交流の種をまく、などの理由を付けて、いろいろな趣向をこらした中国への修学旅行が行われている。
受け入れる中国側は、大歓迎である。何の警戒の必要もない子供たちが来て「円」を落としてくれるからであることは勿論だが、大歓迎の真意はもっと深いところにある。
中国は、修学旅行で訪れるのを奇貨として、日本の子供たちの意識を「反日」という形に変化させて日本に送り返すという作業を、国家政策として遂行しているのだ。「中国に足を踏み入れたからには“日本嫌い”にせずにはおかない」そして「日本崩壊に向けて出撃させる」という戦略なのだ。
この戦略のための恰好の武器として「南京屠殺館」であるとか、各地の「抗日記念館」であるとかという施設が都合よく使われている。
これらは、かつての日本軍が多数の中国人を虐殺したなどと、根も葉もないことを写真展示などビジュアルな形にして見せて宣伝する建造物である。「過去を直視できない者は未来を語る資格はない」などと勝手な埋屈をつけて、虚構と現実の境目をなくそうとするもので、それ自体、いうなら「お化け屋敷」のようなものなのだ。
確かに南京では、二千人であるとか三千人の便衣兵が射殺された事実はある。しかし、それが十万人になり二十万人になり、三十万人と主張する。日本の外務省、文部科学省、教育界は中国の主張に追従し、今度は、何を根拠にしたかは定かではないが、高校教科書に「四十万人説」までもが登場するという有様だ。
言葉狩り
修学旅行を逆手に取る中国の戦略が、どこから生まれたかといえば、ヒントになっているのは「人民公社」であり、旧ソ連の「ピオニール」(共産主義少年団)である。つまり、子供を使って体制を揺さぶり、崩壊させるというやり方なのだ。
モスクワ郊外に旧ソ連の「クートベ」(極東勤労者共産主義大学)というのがあった。世界の共産党員を集めて革命を教えるのだが、暗殺の仕方や盗聴の方法まですべて教えた。「クートベ」で教育を受け、破壊工作を身に付けた共産党員は筋金入りになって出身国に戻り、第三インターナショナルだとか第四だとか勝手な名前を付けた国際共産主義運動のもとに活動を展開した。
そのときに、本国に戻った彼らが一番手っとり早いやり方としてとった方法は、子供を使って親を根絶やしにするということだった。
そのために子供をどう教育したかというと、八ヶ月くらい親から離して集団教育をする。あなたたちのお父さん、お母さんをよくご覧なさい。反動思想の持ち主かどうかは日常の言葉に表れるから、旧思想の残滓は必ず言葉に片鱗が出るから、と教え込んで密告を奨励した。「親が差別発言をしたら、すぐ言え」と棒グラフを使うなどして子供の中での競争原理を巧みに利用し、数を競わせたのだ。「言葉狩り」である。その手法の原型が「ピオニール」にあることはいうまでもない。
これが毛沢東の中国では文化大革命であり、三千万人が殺された。子供が競い合って密告し、親やインテリ層が殺された。子供は英雄になった。
中国はソ連から学んだ手法をカンボジアのポル・ポトに伝授した。ポル・ポトは、中国以上に忠実にこの手法を実行し、百五十万人近いといわれる同胞を殺している。
しかし、日本では事情が違う。日本の生活慣行からは、ソ連、中国、カンボジアのような合宿的集団教育はありえず、文部科学省にしても、児童・生徒を根こそぎ動員できる権限は持っていない。従って「ピオニール」的手法は取れない。
悔しがった当時の日教組は、そこで「反抗期」という用語を造語して、日本にしかない概念を発明した。